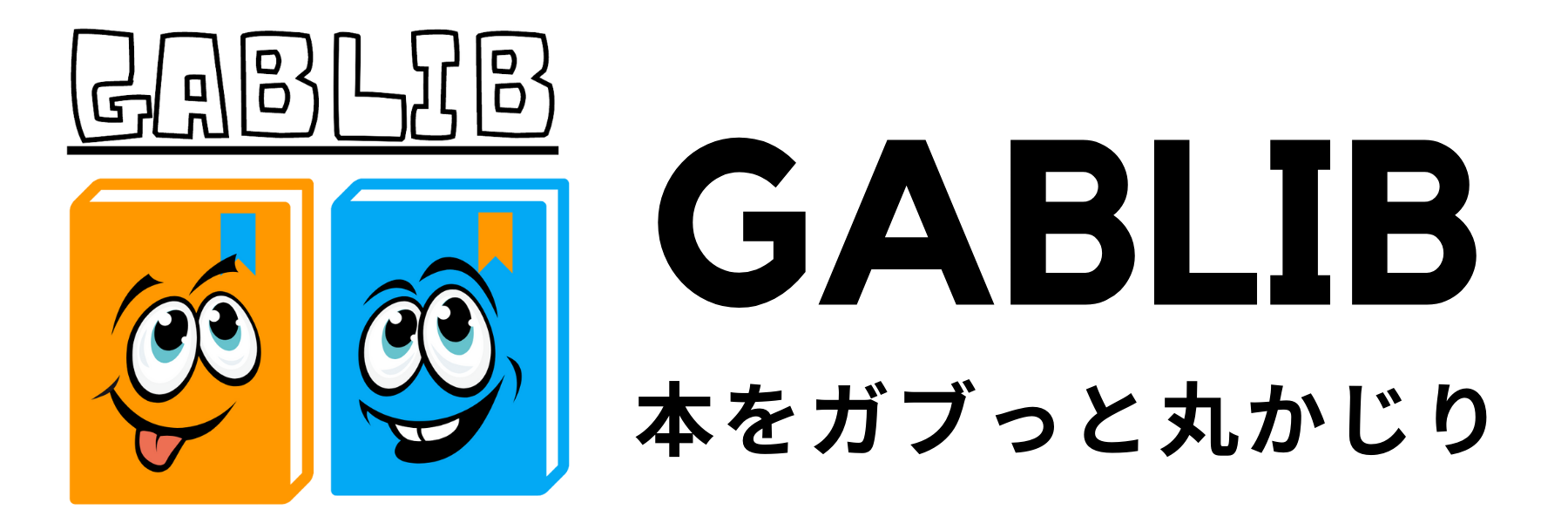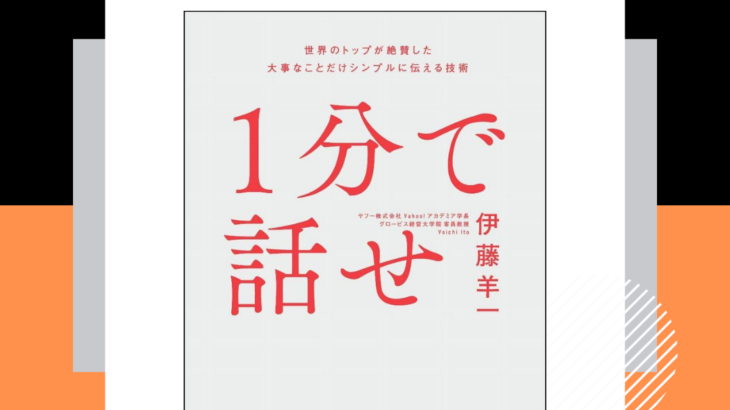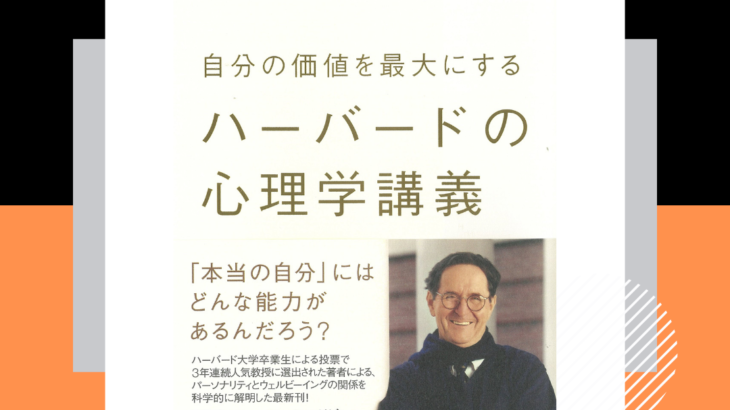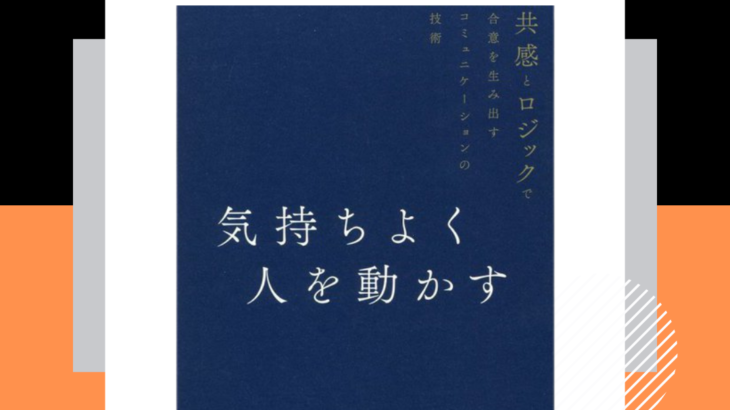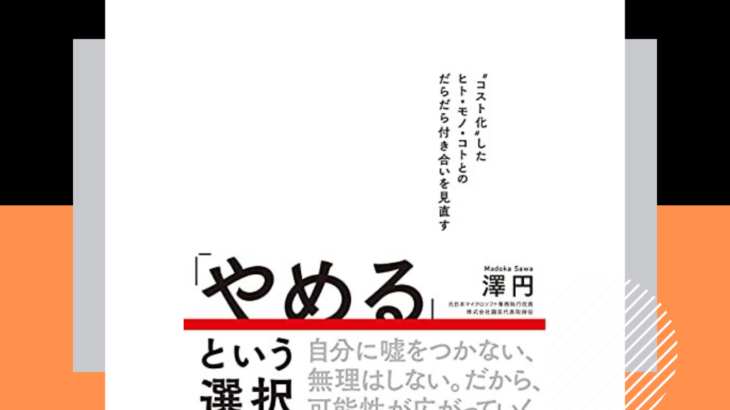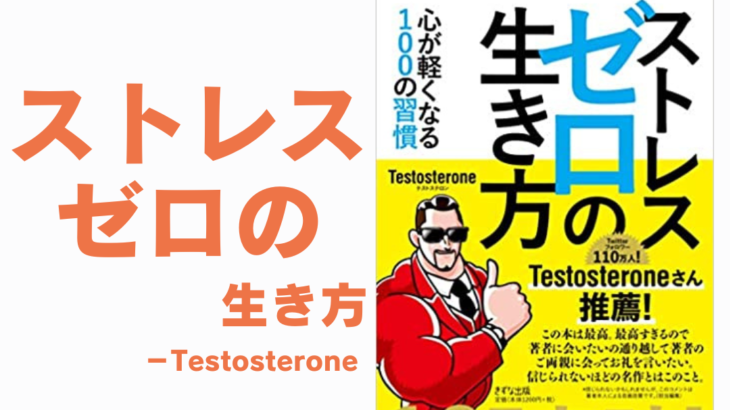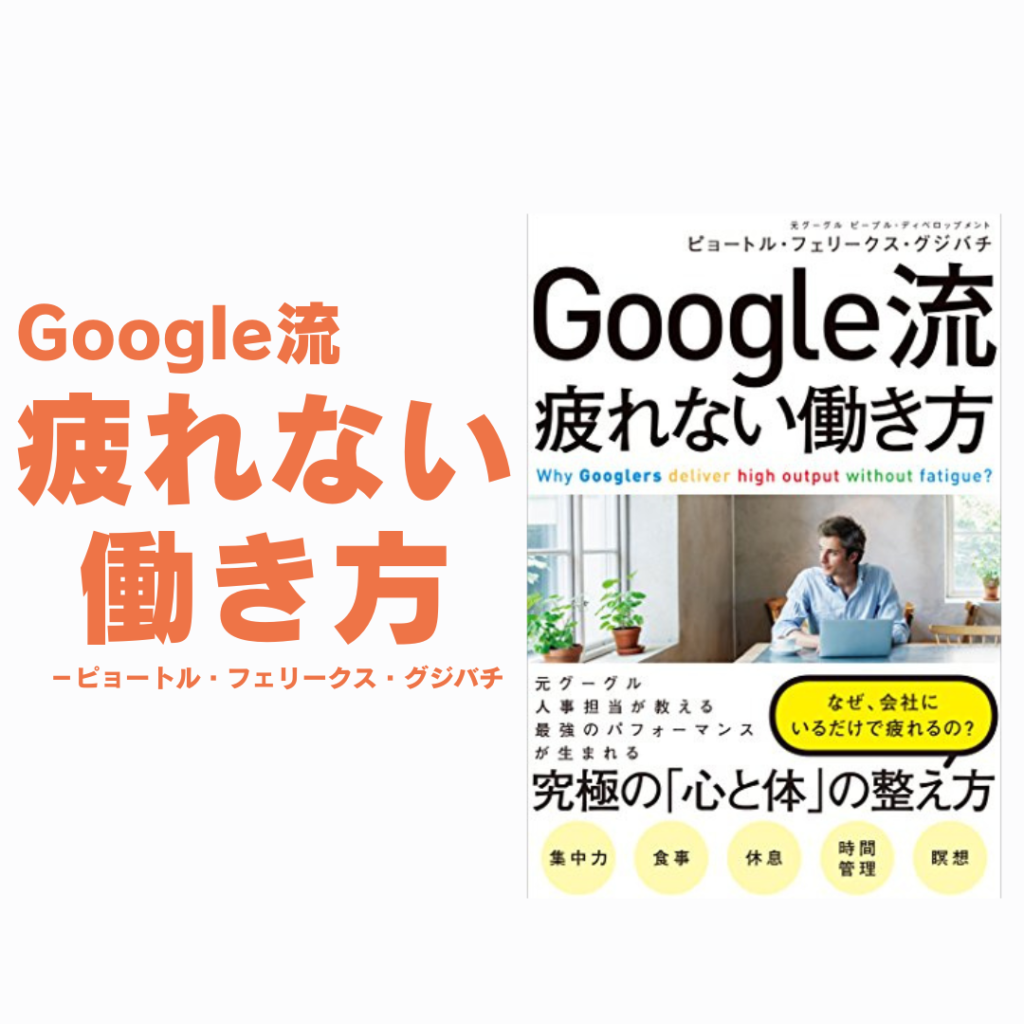
はじめに
総評
懸命に働いているのに、成果につながっている実感がない、、
そんな悩みを抱える皆さんが疲れすぎずに成果を上げていくためのヒントが詰まっている一冊です。
章立てもわかりやすく読書初心者や久しぶりの読書にもお勧めできます。
オススメの読み方
まずは個人レベルで実行ができそうなことを見つけていくことをお勧めします。
最初から組織全体で変化を与えていくことを目指すのはかえって大きな負担になりかねません。自分で試してみたい!と思えるものを見つけながら読み進めてください。
こんな方にオススメ!
・毎日終業後には疲労感でいっぱいになっている方
・休んでも休んでも疲れが抜けなくて、休み明けの出勤が億劫な方
・チームメンバーは懸命に取り組んでいるが、成果を感じさせてあげられている自信がなく組織風土の今後が不安なリーダーやマネージャーの方
著者紹介
著者のピョートル・フェリークス・グジバチさんはポーランド出身でドイツ・オランダ・アメリカで暮らし2000年に日本に来日されました。2002年より英会話教室事業などを展開するベルリッツにてグローバルビジネスソリューション部門アジアパシフィック責任者を経て、2006年より、モルガン・スタンレーにてラーニング&ディベロップメントヴァイスプレジデント、2011年よりグーグルにてアジアパシフィックでのピープルディベロップメント、更に2014年からはグローバルでのラーニング・ストラテジーに携わり人材育成と組織開発、リーダーシップ開発などの分野で活躍をされてきました。
その後独立され、現在は組織開発や人材開発を主とするプロノイアとモティファイの2社を経営されています。
人材開発・組織開発に関連するメディア出演やセミナー活動も活発に行われております。
【講演テーマの例】
- 働き方イノベーション〜これからの働き方・生き方
- リーダーとして、パフォーマンスを上げる〜心理的安全性、信頼関係の築き方〜
- NEW ELITE〜あなたはどう働く?個人が活きる組織をつくる働き方とは〜
- ニューパラダイム〜今問われる働き方・生き方〜
ポイント解説「ここを読め!」
①「タイムマネジメント」から「集中力のマネジメント」へ
高いアウトプットを出すために必要なことはシンプルに「集中すること」であると記されています。その中でも本著においては作業に没頭できる生産性の高い時間「フロー」に入るために大切なことを個人・集団の側面から紹介しています。
この記事では冒頭にも「まずは個人でできることを」と記しましたので、その個人編を紹介いたします。
【個人がフローに入るための7要件】
〜心理的な要件:目の前の状況に意識を集中させるために整えるべきこと〜
・明確な目標「今、何に取り組んでいるのか」「何のために取り組んでいるのか」を具体的に自覚する
・リアルタイムのフィードバック:明確な目標に対し「どうしたらそれをもっと上手くできるか」をリアルタイムに把握し、結果と行動の因果関係を常に掴んでおく
・難易度と能力のちょうど良いバランス:タスクの難易度を、怯むほどではないが「少し手を伸ばせば届く」程度に調整する
〜環境的な要因:整えるべき周辺環境〜
・大きな影響力のある課題設定:ハイリスク・ハイリターンな挑戦を設定する
・ワクワクする環境:「新規性」「予測不可能性」「複雑性」の3要素が高い環境を作る
・全身が没入できる環境:全身を動かして五感をフルに活用しながら、タスクに取り組める機会を作る
〜想像的な要件〜
・パターンに気づき、パターンを壊す
(Piotr Feliks Grzywacz , 2018 ,27-30)
②エネルギーと感情をマネジメントする
より良い仕事のパフォーマンスを発揮するために、自身のエネルギーと感情をマネジメントすることが重要であると述べています。
書籍で紹介されている事例や私が読み進める中で良い結果が生まれそうな事例を一部紹介します。
・自身の今のエネルギーを把握する
→無理をし過ぎていないか、取り組もうとしている業務は現状のエネルギーで進めることが可能か
・仕事をする環境に合わせて取り組む内容を調整する
→雑音が多い場所でのアイディア出しや満員電車内でのスマホ作業など余計なエネルギーを使わざるを得ない環境にいないか
・エネルギーを溜めるための時間を確保する
→休養・栄養などに限らず、好きな音楽を聴ことや、好きな場所へ足を運ぶこと、好きな洋服を着ることなど
自分の状況を正しく把握し(過度に我慢をし過ぎない)、状態に合わせて柔軟に取り組みを決め、エネルギーが不足している時は蓄えるための時間を作ることが大切とされています。
書籍の中ではGoogle社員が実際に取り組んでいるエネルギー・感情をマネジメントするためのスケジュールの設計方法なども紹介されています。
本著は2018年に出版されていますが、現在のコロナ禍における就業環境の変化を受けてチャレンジしやすいものが数多く紹介されています。
③心理的安全性を担保する
最後は組織として整えていく必要があるポイントです。いくら個人が良い習慣を身につけて良い準備をしてきたとしても、組織に問題があっては良いパフォーマンスにつながりません。人間は集団で社会を築いて生きていきます。この根本はリモートワークが浸透した昨今においても変わりません。信頼できる人たちとの良好な関係で安心を手に入れるようになります。
本著の中ではこの環境を整備するために必要なことが「他者を含めたマインドフルネス」としています。一般的にマインドフルネスは個人のコンディションを整えることに用いられることが多い言葉ですが、著者は日本語で表現するならば「思いやり」であるとも記しています。
これを達成するプロセスは以下のように紹介されています。
1「Sympathy」:同情
→困っている人に対して、可愛そう・気の毒だなという気持ちを持てること
2「Empathy」:共感
→相手の悩みや大変さを自分ごととして捉えること
3「Compassion」:思いやり
→相手を助けてあげたいという気持ちを持つこと
(Piotr Feliks Grzywacz , 2018 ,147-149)
そしてこのCompassionを他社から受けたときに、人は心理的安全性を感じるとされています。
自分の集中力・エネルギー・感情のマネジメントができた先には他者を巻き込んだ変化に挑戦していくフェーズに入っていくということになります。
まとめ
さて、今回ご紹介した「Google流 疲れない働き方」ですが、出版は2018年と3年前のものになります。
しかしながら、昨今の新型コロナウイルスの影響によりこれまでの当たり前の就労環境は強制的に大きな変化を遂げることとなりました。出社することが前提ではなくなり、個々人で質の高いセルフマネジメントができることが重要な働き方へ変化をしてきています。大切に繋ぎたい理念・文化を継承しつつ、個人がより良いキャリアを築いていくためのヒントが詰まった一冊となっています。